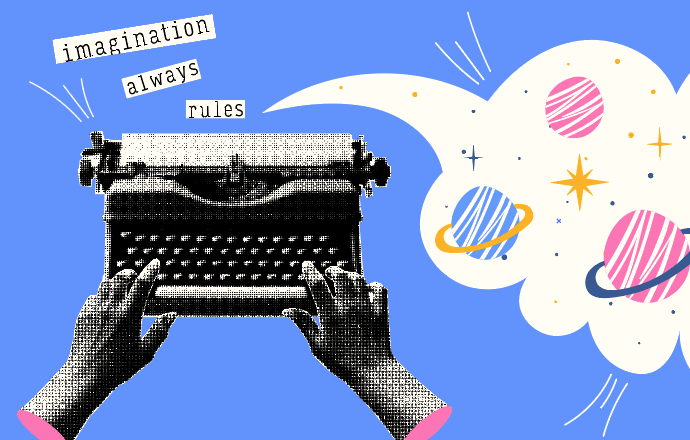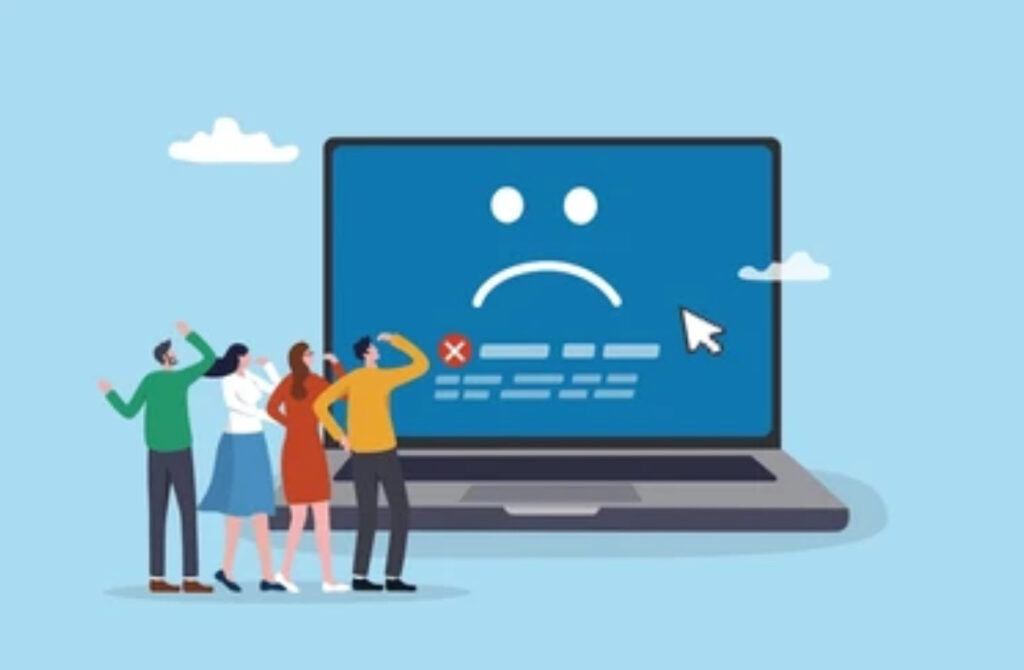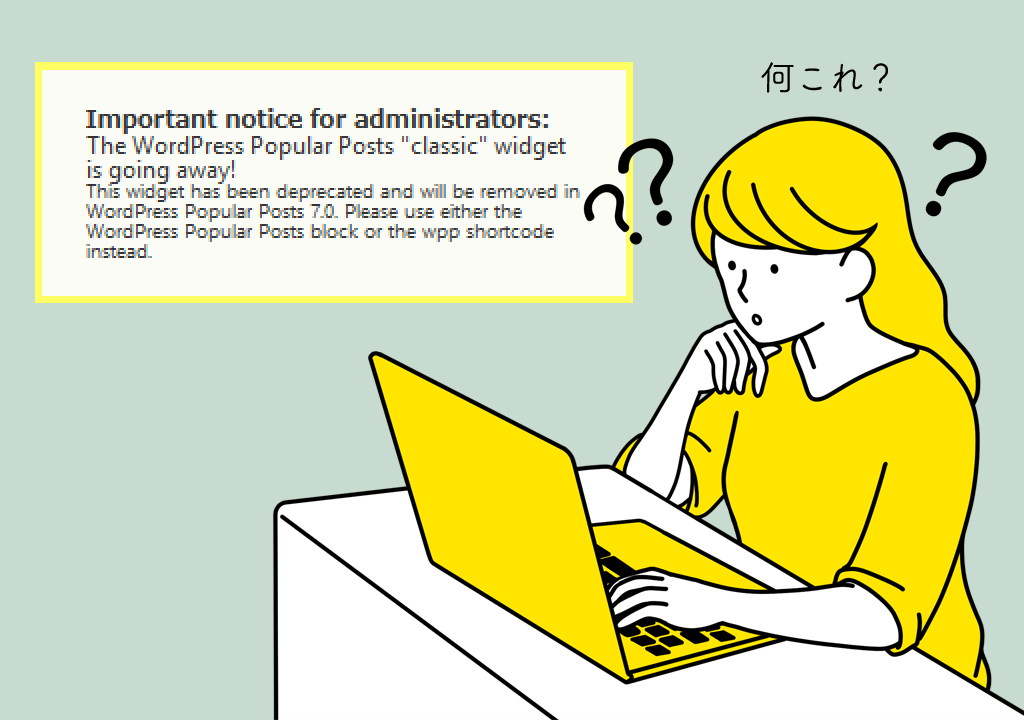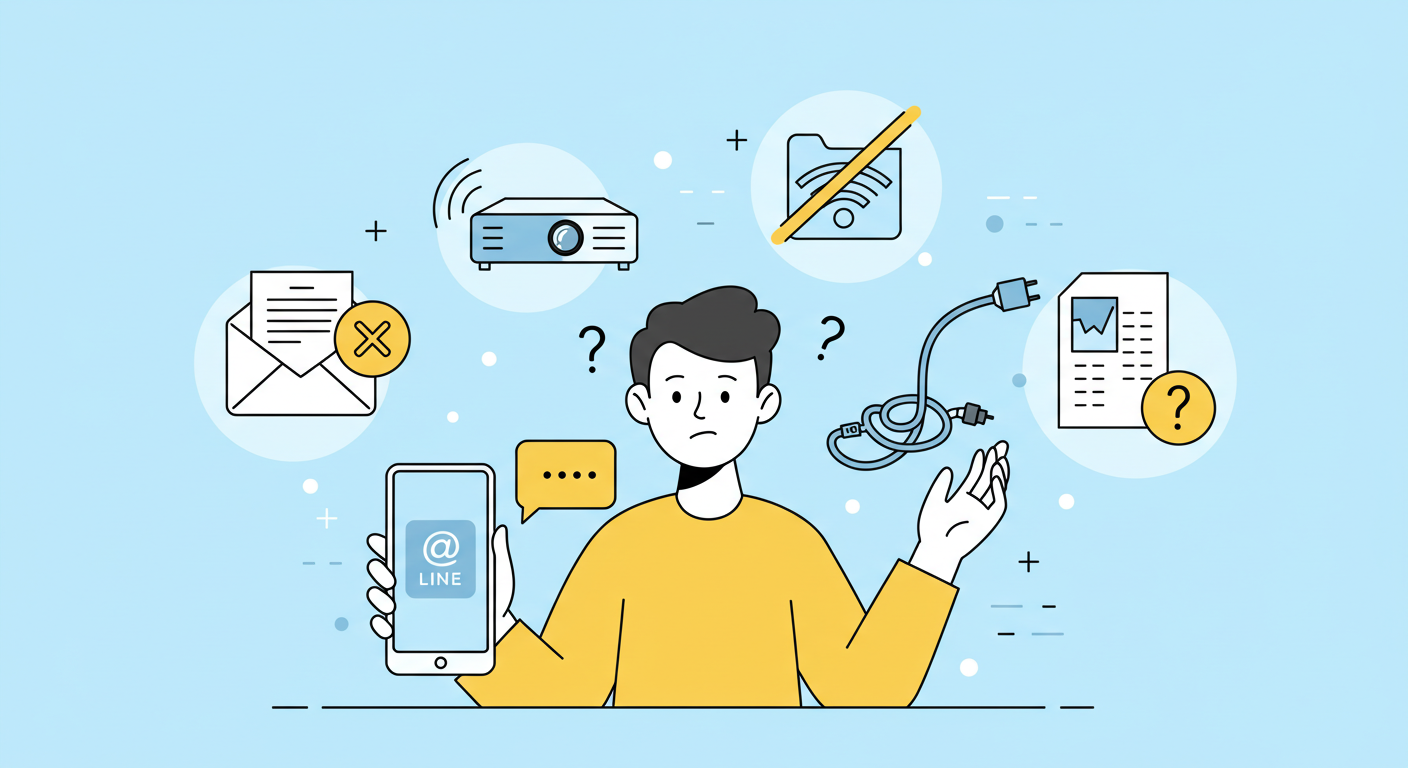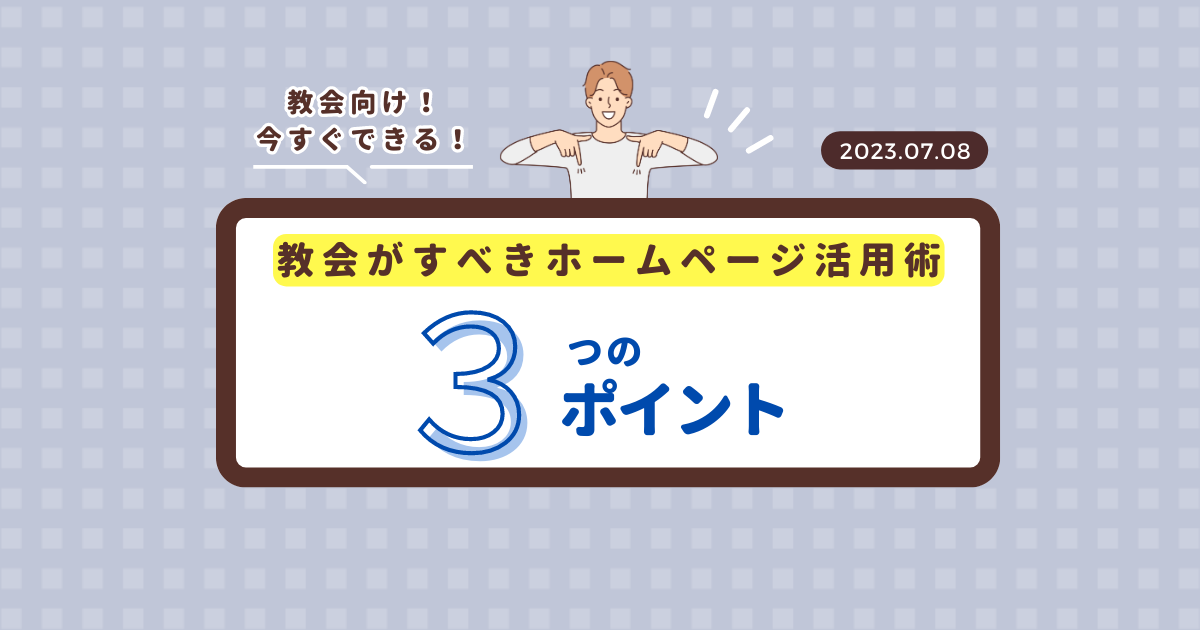ブログを書いているけれど、「なんだか文章がまとまらない」「読者に伝わっているか不安」と感じることはありませんか?お客様からもよく聞かれるんです。
実は、多くのブロガーが抱えるこの悩みは、「PREP法」という文章の書き方を覚えるだけで解決できます。PREP法は、結論を最初に述べて、理由と具体例で説明し、最後にもう一度結論で締めくくる構成方法です。
この記事を読めば、PREP法の基本から実際の使い方まで、ブログ初心者でもすぐに実践できる内容が身につきます。文章を書くのが苦手な方でも、この方法を使えば読みやすく説得力のある記事が書けるようになります。
それでは、PREP法を使った効果的なブログの書き方を詳しく見ていきましょう。
PREP法とは何か?基本の「き」から理解しよう
PREP法とは、文章を分かりやすく構成するためのフレームワークです。この名前は、4つの英単語の頭文字から作られています。
- P(Point):結論・要点
- R(Reason):理由・根拠
- E(Example):具体例・事例
- P(Point):結論・要点(再度)
普段の会話でも、「結論から言うと〜」と話し始める人の話は分かりやすいですよね。PREP法は、その分かりやすさを文章でも実現する方法なのです。
PREP法の流れを具体的に説明
PREP法では、以下の順序で文章を組み立てます。
- 最初のP(結論):読者が一番知りたいことを最初に伝える
- R(理由):なぜその結論に至ったのかを説明
- E(具体例):理由を裏付ける事例やデータを示す
- 最後のP(結論):改めて要点を強調して締めくくる
この構成にすることで、読者は「何を言いたいのか」をすぐに理解でき、その後の説明も頭に入りやすくなります。
なぜPREP法がブログに効果的なのか
PREP法がブログライティングに適している理由は、主に3つあります。
読者の時間を大切にできる
現代の読者は忙しく、長い前置きを読む時間がありません。PREP法なら最初に結論を示すため、読者は記事の価値をすぐに判断できます。「この記事は自分の求めている情報がありそう」と感じてもらえれば、最後まで読んでもらえる可能性が高まります。
説得力のある文章が書ける
結論に対して理由と具体例を示すPREP法は、論理的な文章構成になります。感情的な文章ではなく、客観的な根拠に基づいた内容になるため、読者の納得感が得られやすくなります。
文章を書くスピードが上がる
PREP法という型があることで、「何から書けばいいか分からない」という状況を避けられます。まず結論を決めて、その理由を考え、具体例を探すという手順が明確なため、迷わずに文章を進められます。
PREP法を使った実際の文章例
PREP法の効果を実感していただくために、同じテーマで2つの文章を比較してみましょう。
PREP法を使わない文章例
「最近、在宅ワークをする人が増えています。通勤時間がなくなったり、家族との時間が増えたりと、様々な変化があります。一方で、集中力が続かないという声も聞きます。実際に私の友人も、家では仕事モードに切り替えられないと言っていました。でも、工夫次第で在宅ワークの生産性は向上させることができると思います。」
PREP法を使った文章例
P(結論):在宅ワークの生産性は、環境づくりで大幅に改善できます。
R(理由):なぜなら、集中力の低下は主に「仕事とプライベートの境界が曖昧になること」が原因だからです。
E(具体例):例えば、専用のワークスペースを作る、仕事用の服に着替える、開始と終了の時間を決めるといった工夫をした人の多くが、オフィスと同じレベルの集中力を取り戻しています。
P(結論):つまり、適切な環境を整えることで、在宅ワークでも高い生産性を維持できるのです。
どちらが分かりやすく、説得力があるかは一目瞭然ですね。
ブログでPREP法を活用する具体的な方法
PREP法をブログに取り入れる際は、記事全体の構成と、各段落の構成の両方で活用できます。
記事全体でのPREP法活用
記事のタイトルや導入部分で結論を示し、見出しごとに理由や具体例を展開し、最後のまとめで再度結論を強調する構成にします。
P(結論):タイトルと導入で記事の結論を明示 R(理由):H2見出しで「なぜそう言えるのか」を説明 E(具体例):H2やH3見出しで事例やデータを紹介 P(結論):まとめで記事の要点を再確認
段落レベルでのPREP法活用
各見出し内の文章も、PREP法で構成すると読みやすくなります。一つの見出し内で一つの主張をして、それを理由と具体例で支える形です。
PREP法を使う時の注意点
PREP法は非常に有効な手法ですが、使い方には注意が必要です。
すべての文章に適用する必要はない
ストーリー性を重視したい記事や、感情に訴えかけたい内容では、PREP法が適さない場合があります。読者の心に寄り添うような文章では、起承転結の方が効果的なこともあります。
単調になりすぎないよう工夫する
すべての段落をPREP法で書くと、文章のリズムが単調になる可能性があります。重要な部分でPREP法を使い、その他の部分では自然な流れを意識するとよいでしょう。
読者の感情を無視しない
PREP法は論理的な構成ですが、読者の感情を完全に無視してはいけません。共感できる表現や、読者の立場に立った言葉選びも大切です。
PREP法以外の文章構成も知っておこう
PREP法と合わせて覚えておくと便利な文章構成をご紹介します。
SDS法
SDS法は「Summary(要約)→Detail(詳細)→Summary(要約)」の構成です。PREP法よりもシンプルで、短い文章に適しています。
起承転結
日本人に馴染み深い構成で、物語性のある文章や感情に訴える内容に適しています。ブログでも、体験談などで効果を発揮します。
まとめ:PREP法でブログの質を向上させよう
PREP法は、ブログ初心者でも簡単に習得できる文章構成の手法です。結論を最初に示すことで読者の関心を引き、理由と具体例で説得力を高め、最後に再度結論を示すことで記憶に残りやすくなります。
この方法を使うことで、「何が言いたいか分からない」と言われがちな文章から卒業し、読者に価値を提供できるブログが書けるようになるでしょう。
最初は慣れないかもしれませんが、何度か練習すれば自然に使えるようになります。ぜひ次の記事からPREP法を意識して、読みやすく説得力のあるブログを作成してみてください。